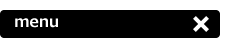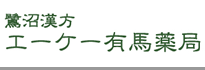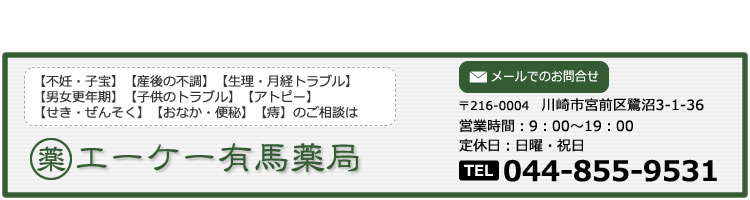予防養生
予防養生
体の予防養生
胃もたれ・膨満感・ゲップ・胃酸逆流は「胃下垂」「胃アトニー」かも
ドライアイで困っている方はぜひ読んでください「洗肝明目湯(せんかんめいもくとう)」
あなたの生理痛はどのタイプ? これを見ればわかる!生理痛4つの体質
「卵子の在庫とAMH検査」 若奥さんのブログ20170311
「不妊カウンセラー体外受精コーディネーター養成講座に参加しました」 若奥さんのブログ 20161005
BMI22が最も病気にかかりにくいというけど 若奥さんのブログ 20160809
シミ・シワの改善にも冠元顆粒がいいですよ 若奥さんのブログ 20160729
ビスホスホネート系薬とカルシウムについて思うこと 若奥さんのブログ 20160709
心の予防養生
疲れているのに眠れない方はぜひ読んでください!不眠の漢方薬「帰脾湯」
「抗うつ剤と胃薬と抗プロラクチン血症の関係」 若奥さんのブログ 20160716
「ストレスと妊娠について」若奥さんのブログ 20160714
季節の予防養生
冷えると膝や腰が痛くなる方はぜひ読んでください!膝腰の漢方薬「独歩顆粒(どっぽかりゅう)」
舌に歯形が付く方はぜひ読んでください!胃腸疲れを回復する漢方薬「六君子湯」
「頭が重い」「体がだるい」「食欲がない」困ったときの漢方薬「かっ香正気散(かっこうしょうきさん)」
夏の終わりのめまいと脱肛と皮下出血 若奥さんのブログ 20160819
「夏の疲れと二人目不妊」 若奥さんのブログ 20160806
食の予防養生
漢方薬と薬膳茶の違いって? 若奥さんのブログ 20160921
アイスクリームと温かい金花黒茶 若奥さんのブログ 20160824
「葉酸補給もできるおやつに、なつめはいかがですか?」 若奥さんのブログ 20160723
漢方の予防養生
こむらがえりの漢方薬「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」は素早く効く!
エーケー有馬薬局漢方体験【更年期のホットフラッシュと逆流性食道炎】
エーケー有馬薬局漢方体験【動悸・息切れ・鼻水がのどに落ちる】
「早期閉経 (POF)って?」 若奥さんのブログ 20161001
「産後のケアにも婦宝当帰膠」 若奥さんのブログ 20160917
「不妊症セミナーに出席しました」 若奥さんのブログ 20160830
宿題がはかどるかもしれない、シベリア人参 若奥さんのブログ 20160816
頭皮の皮脂、気になりませんか? 若奥さんのブログ 20160712
わき汗、足の臭い対策にいいものがあります オドレミン 若奥さんのブログ 20160706
こどもにも薬が必要な時と場合 若奥さんのブログ 20160704
「妊活に当帰芍薬散がいいのか?婦宝当帰膠がいいのか?」 若奥さんのブログ 20160702
頭痛薬だけじゃもったいない頂調顆粒 若奥さんのブログ 20160624
白髪、薄毛、髪の毛にいいもの 若奥さんのブログ 20160618
「精液検査で問題ないは本当に問題ないのか?」 若奥さんのブログ 20160616
「妊活はご主人も一緒に」 若奥さんのブログ 20160612
毛髪診断講習会に行ってきました 若奥さんのブログ 20160523
「タイミングをとるのにいい日について」 若奥さんのブログ 20160405
ファスティングしてみた 若奥さんのブログ 20150928より
夏の疲れは髪に来ると思う 若奥さんのブログ 20150727
ちょっと怖い、薬の話 若奥さんのブログ 20150717より
春・肝臓・ワタナベオイスター 若奥さんのブログ 20150223より
洗濯石けんで思うこと 若奥さんのブログ 20141128より
こどものお薬あります 若奥さんのブログ 20141126より
漢方の予防養生
むくみの養生法
むくみは、体に水分(正確には血液以外の体液)が多すぎてあふれている状態です。日本は四方を海に囲まれているため、ヨーロッパなど乾燥した土地と違い、湿気が多くジメジメした土地です。そのため、皮膚からの発汗量が少なく、体の中に水が留まりやすい土地と言えます。特に、梅雨や蒸し暑い夏にむくみが多く起こります。「重だるい」のが特徴です。
その1、「水分のとりすぎ」タイプ
「原 因」水分のとりすぎで、体の中に余分な水分が溜まってしまい、むくみを起こします。余分な水は胃腸の働きを弱らせ、さらにむくみを強くします。
「症 状」胸がムカムカして、頭が重く、全身がだるくなります。下半身がむくむようになり、ひどくなると、全身がむくみます。量が少なく、色の薄い尿が出るようになります。
「予防法」まず、水分のとりすぎを控えましょう。運動や家事などで積極的に体を動かし、気持ちの良い汗をかいて余分な水分を汗として排泄するのも良いでしょう。
「食養生」にがうり、とうがん、とうもろこし、はと麦など胃腸の働きを高めて、体の中の水分の巡りを良くする食材を食べましょう。
その2、「胃腸が弱い」タイプ
「原 因」もともと胃腸が丈夫でない人は、体の中の水分をさばく力が弱く、むくみを起こしやすい体質です。冷たいものをとると、すぐ下痢をしてしまうタイプの人です。
「症 状」疲れやすく、尿の量が少なくなります。おなかや手足の冷えがあり、肌がプヨプヨして、押すとへこんで、なかなか元に戻りません。
「予防法」消化の良いものを食べて、胃腸の働きを回復させましょう。全身を温めておなかの冷えを改善しましょう。マッサージで水分の巡りを良くしてあげるのも良いでしょう。
「食養生」もち米、そら豆、えんどう豆など胃腸の働きを良くして、水分の巡りを良くする食材を食べましょう。
その3、「腎が弱い」タイプ
「原 因」腎の機能が弱ると、余分な水分を尿として排出することができず、むくみを起こしやすくなります。
「症 状」下半身にむくみを起こすことが多く、内くるぶしなどがよくむくみます。手足や全身が冷え、疲れやすくなったり、また、腰や膝がだるくなり、ガクガクしたりすることもあります。
「予防法」全身を温め活力を取り戻しましょう。冷えや水分のとりすぎは厳禁です。
「食養生」うなぎ、えび、くり、くるみなど腎の働きを高める食材を食べましょう。
参考図書:図解よくわかる東洋医学
【不妊・子宝】【産後の不調】【生理・月経トラブル】【男女更年期】【子供のトラブル】
【アトピー】【せき・ぜんそく】【おなか・便秘】【痔】のご相談は
東急田園都市線 鷺沼駅 川崎市宮前区の漢方相談薬局
【エーケー有馬薬局】までご相談ください